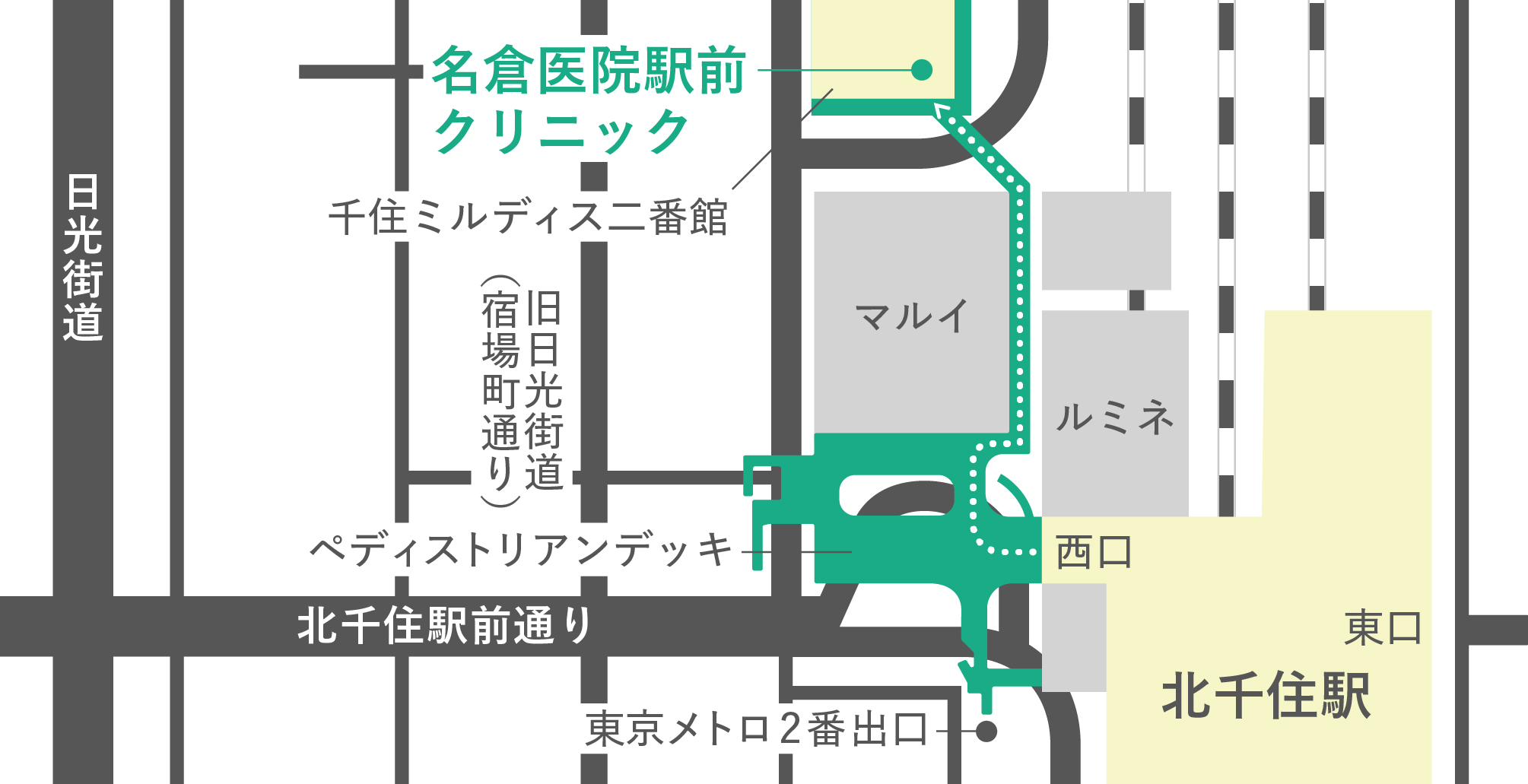頚椎後縦靭帯骨化症

「最近、首がこる」「手にしびれを感じる」「歩くときにつまずきやすくなった」――これらの症状が、単なる加齢や疲れのせいではなく、頚椎後縦靱帯骨化症(けいついこうじゅうじんたいこっかしょう)という病気のサインであることがあります。
疾患の概要について
頚椎後縦靱帯骨化症(OPLL)は、頚椎の椎体後面に沿って存在する「後縦靱帯」という靱帯が、骨化(本来柔軟な組織が骨組織へと変性する現象)を起こし、脊髄や神経根を圧迫することにより様々な神経症状を引き起こす疾患です。
後縦靱帯の骨化は、脊柱管内(せきちゅうかんない)で起こるため、圧迫されるのは皮膚に近い背側ではなく、脊髄の前方となります。この圧迫が進行すると、しびれや筋力低下、歩行障害、さらには排泄障害などの深刻な症状が現れることもあります。
主な症状
✅ 首の痛みや不快感
✅ 手や指のしびれ
✅ 脱力箸を使う
✅ ボタン留など細かい動作が困難になる
✅ 歩行時のふらつきやつまずき
✅ 排尿・排便コントロールの障害
こうした症状はゆっくりと進行する傾向があり、「年齢のせいかな」と見過ごされやすいのが特徴です。症状に少しでも心当たりがある場合は、早めに整形外科や神経外科の受診をおすすめします。
原因と危険因子
頚椎後縦靱帯骨化症の発症メカニズムは完全には解明されていませんが、以下のような因子が関与すると考えられています。
■ 遺伝的要因
家族に同様の疾患がある場合、発症リスクが高まることが報告されています。
■ 人種的背景
日本をはじめとする東アジア人に多く見られ、欧米人では比較的少ない傾向にあります。
■ 生活習慣・姿勢
長時間にわたるデスクワークやスマートフォン操作、不良姿勢、睡眠時の首への負荷などが関係する可能性があります。
■ 代謝性疾患
糖尿病などの代謝異常がある方では、後縦靱帯の骨化が起こりやすいという報告があります。
■ 年齢・性別
40歳以降に発症することが多く、男性は女性の約2倍の頻度でみられます。
また、本疾患は頚椎症性脊髄症や脊柱管狭窄症など、他の脊椎疾患と合併して見られることもあります。
診断と治療法
◯ 保存療法(手術を行わない治療)
症状が軽度であり、日常生活に大きな支障がない場合には、保存的治療から始めます。
・消炎鎮痛薬(痛みや炎症の緩和)
・ビタミンB12製剤など神経保護薬
・頚椎カラー(首のサポーター)による安静
・物理療法(温熱、牽引など)
・姿勢指導や筋力強化を中心としたリハビリテーション
これらの治療を組み合わせながら、症状の進行を防ぎ、神経機能の温存を目指します。
◯ 手術療法
保存療法で効果が得られない場合や、症状が進行している場合には手術が検討されます。
手術の目的は、脊髄や神経の圧迫を除去し、進行する麻痺を食い止めることです。主な術式には以下があります。
・前方アプローチ:頚部の前面から骨化部分を直接除去
・後方アプローチ:椎弓形成術などで脊柱管を広げる
・前後方併用術:広範囲な骨化や複雑な症例に対して実施
手術方法は、骨化の範囲や進行度、患者さまの全身状態などを総合的に判断して選択されます。近年は顕微鏡やナビゲーションシステムを用いた精度の高い手術が増えており、安全性と術後成績の向上が期待されています。
◯ 術後のリハビリと生活管理
術後は、神経の回復と生活機能の維持を目的としたリハビリテーションが不可欠です。
・筋力トレーニング
・歩行訓練
・日常生活動作の再学習
多くの場合、3〜6ヶ月程度で日常生活に復帰可能ですが、職種や年齢、症状の程度により回復期間には個人差があります。
また、再発や悪化を防ぐためには、以下のような生活管理が重要です。
✅ 正しい姿勢の維持
✅ 適度な運動習慣の継続
✅ 重い物を持つときの工夫
✅ 質の良い睡眠
✅ 環境の確保バランスの取れた食生活
まとめ
頚椎後縦靱帯骨化症は、進行性の神経障害を引き起こす可能性がある疾患です。症状が軽度でも、早期発見・早期治療によって、進行を防ぎ、生活の質を保つことができます。
当院では、整形外科専門医による精密な診断と、患者さま一人ひとりに合わせた治療方針の提案を行っております。少しでも気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。
当院のご紹介
症状やご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
およそ250年前から千住の地で親しまれてきた名倉医院の分院として、その歴史の中で培われた知識や技術を土台として最新の医療を提供しております。
※手術やより高度な治療が必要と判断された場合は、適切な医療機関へご紹介させていただいております。